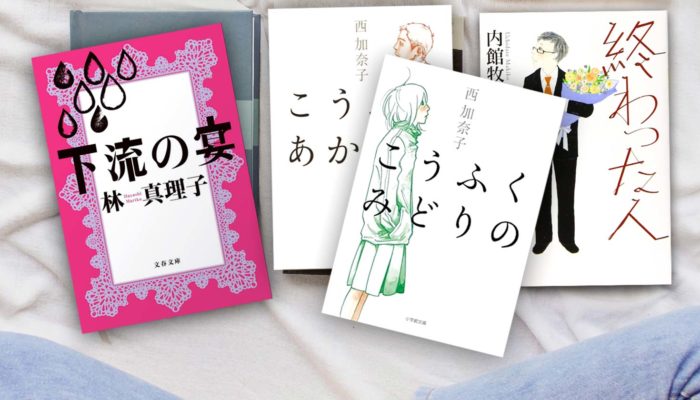Blog
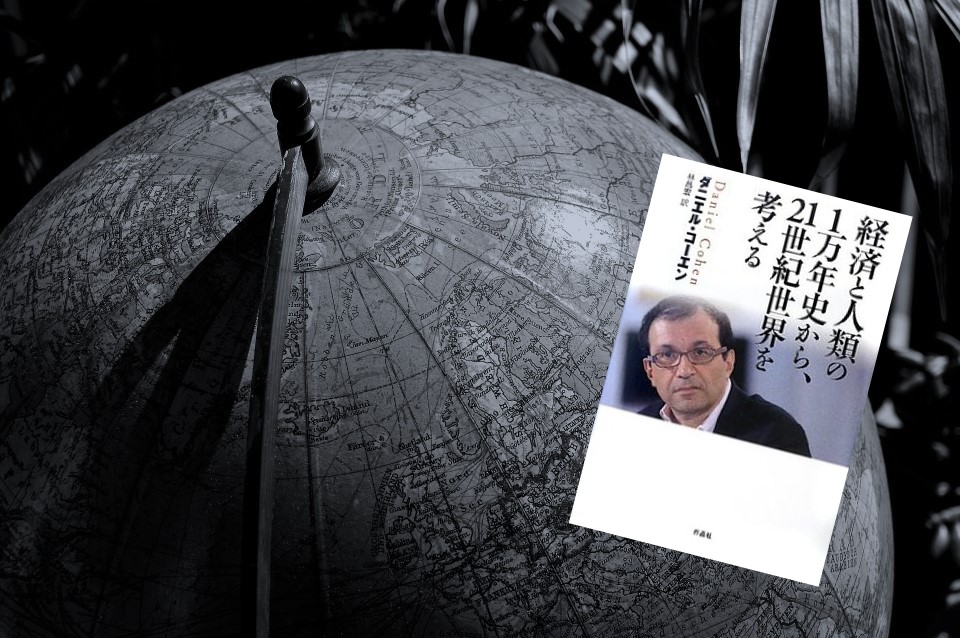
現代の「常識」は正しいか?
ダニエル・コーエンの「経済と人類の一万年史から、21世紀世界を考える」を読んでのまとめです。これは良書だった。
私たちには「これが常識だよね」と自然と感じる感覚があります。そして、常識に反する事象に直面すると、違和感や嫌悪感を感じます。
「常識」は英語では”Common sense”、つまり共同体(Common)の感覚(Sense)と言います。これは、何を「常識」として考えるかは、どの共同体に属しているのかよって変わってくるということを意味します。
一方で、「常識」は私たちの無意識の領域に刷り込まれているので、それを疑うことが困難です。子供に「なんで〇〇しちゃいけないの?」と聞かれて「それが常識なんだよ」とは言うものの、どうしてそれが常識なのか、説明できずに困ってしまったという経験がある人は多いと思います。
我々がどういう「常識」を無意識の中に持っているのか、それに気づくためには他の「常識」を見聞きすることが役立ちます。そうすることで無意識が相対化されるからです。そして、現代の常識がどのような背景で成り立っているのかを知るには、「過去の常識」を知ることが役に立ちます。なぜなら、現代はグローバル化が進んでおり、グローバル共通でもってしまっている常識を相対化するためには、現代以外の参照点が必要だからです。
この本は、人類1万年の歴史を紐解くことで、現在の社会経済体制の特徴を明らかにしていく本です。我々は、現在の社会経済体制にどっぷりと浸かっており、かつその巨大な恩恵を受けています。その為、それ以外の体制が有りうるのか、有りうるとしたらどのようなものなのか、想像力が働きにくくなっています。
現在の常識を一旦脇に置き、我々が今後作って行かなければならない社会経済体制について客観的に考える時に、歴史を紐解くことがとてもパワフルだということをこの本は伝えてくれます。
人口減は悪か?
例えば、現在の日本では人口減少が大きな問題とされています。経済成長を考える上で、人口が減るのは好ましくないという議論です。経済成長は、「人口の増減」「資本の蓄積」「生産性の向上」の3つの要素によってもたらされ、人口減は経済成長に直接のマイナスとなり、また人口減となる市場には投資が集まらないので生産性の向上も望みにくくなる、という考え方。
これが正しいかどうかは現代においても異論反論がありますが、多くの人が「人口減少は問題だ」という考えを常識と捉えています。
一方で、かつて経済学に影響を与えていたマルサスの法則では、人口は抑制する必要がある、と考えられていました。なぜなら、人口は等比数列的に増えるのに対して食料生産は等差数列的なスピードでしか増えないと考えられていたからです。人口抑制しないと「人口調整=下層階級の子供栄養失調・死亡」が起こると考えられていました。
実際、江戸時代中期以降の日本の人口は3000万人程度で一定だったと言われていますが、これは農地の生産性上限に達した後、農村部で長男以外を「口減らし」していたためと言われています。
現代の私たちは、人口を如何に減らさないか(=予想よりも増やすか)ということを一生懸命議論していますが、人口が増えても(減らなくても)問題が起こらない為には、いくつかの前提が必要となります。
増える人口を養うための前提条件
そもそも、欧州において人口が増え始めたのは18世紀中頃の産業革命が始まってからのことです。この段階において、マルサスが言っていた「人口の増加と所得の増加は同時には起こりえない」という常識が当てはまらなくなります。産業革命の進むイギリスでは、人口が増加し、同時に所得水準が改善していきます。
その背景にあったのは、「海外からの食糧輸入」と「化石エネルギー(石炭)の活用」です。産業革命以降、イギリスは繊維をアフリカに売り、アフリカは奴隷をアメリカに売り、アメリカが綿花をイギリスに供給する、という三角貿易体制を構築しました。
「分業」は効率的です。アダムスミスは市場に参加するものは全員勝者である、と述べましたが、分業し競争力のある繊維を海外に売ることで、イギリスは増える人口を食べさせる食料を海外から輸入しました。
また、その産業の生産性を高めるために石炭エネルギーが使われました。石炭が使われる前は、使用できるエネルギーは水力や木材など、直接的・間接的に「今」存在する土地に紐づいていました。石炭エネルギーを使うことで「過去」の蓄積を使うことが出来るようになり、マルサスの法則が当てはまらなくなりました。
産業革命を経て、マルサスが依拠していた前提が変化したため、継続的な人口増加が可能になったわけです。
増える人口は今後も本当に養えるのか?
こうして考えると、そもそも、かつて増える人口を養ってきた大きな前提条件が今後も当てはまるのか、ということが重要な論点になってきます。
特に、化石燃料は有限であり、「化石燃料が長期にわたって使える」という前提条件が成り立たなくなると、マルサスの法則が再度当てはまるようになるのではないか、とさえ思います。
現代の問題は複数の前提条件の将来シナリオを同時に考えないと解が出せないようになっています。問題が極めてシステミックなので、ある政策を常識に沿った判断で支持/不支持と決めることは危険です。
歴史を紐解くと、社会システム不全によって滅びた文明をいくつも見ることが出来ます。
世界最古の文明であるシュメールは、大規模な灌漑システムを使ったため広域での地下水位上昇を招きました。その為塩分を含んだ水分の蒸発が起き、大規模な塩害を発生させて滅亡しました。イラク・クウェートの辺りは今でも不毛の土地になってしまっています。
ローマ帝国は、征服地からの奴隷供給と大規模農園の運営、職業軍人の活用で領土を増やしましたが、征服地の減少が奴隷供給の減少を招き、システム不全を起こして滅亡しました。
次の地球規模の失敗は許されない
著者のダニエル・コーエンは、結びの言葉の中で
人類は、孤独な惑星という限りある環境で暮らす術を学ぶために、新石器時代の革命や産業革命のときのように、懸命に努力しなければならない。人類が事後に自分たちの過ちを正すことは、もはや許されない。これは人類史上初のことである
と述べています。
19世紀以降、多くの人文社会学者が、いかに人間の認知能力が限定的か、ということを述べてきました。
私たちが自分の意思・考えと思っているのことの大半は、歴史的・社会的な影響を受けており、また脊髄反射的に反応してしまう例も多くあります。
この個々人の認知能力の限界を超えるためには、対話と学習を通じた客観的な思索を進めて行くしかないのではと思っています。
歴史を紐解いて、それを核に社会で対話を進めて行くことは、個々人の認知能力の限界を超える方法として極めて有効。この本はそんな感覚を思い起こさせてくれる優れた本だと思います。
著者プロフィール
渡邉 寧YASUSHI WATANABE
慶応義塾大学文学部/政策・メディア研究科卒業後、ソニー株式会社に入社。7年に渡りマーケティングに従事。約3年の英国赴任を経てボストン・コンサルティング・グループに入社。メーカー、公共サービス、金融など、幅広い業界のプロジェクトに4年間従事。2014年に独立。2025年に京都大学大学院人間・環境学研究科にて博士号取得。専門は文化心理学、組織行動。最近の研究テーマはAIの社会実装 × 職場の幸福感 × 文化の違い。 経歴と研究実績はこちら。
関連ブログ Related Blog
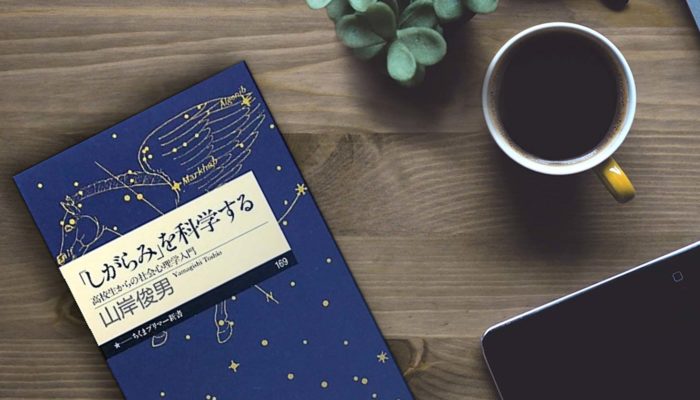
2022.4.19
日本はなぜこうも「しがらむ」のか?- 社会における人々の適応戦略という視点
山岸先生の高校生への語り口 ホフステードの国民文化の研究は、社会心理学の領域に留まらず、経営学等様々な分野で引用され、またアカデミアではない企業などの一般の社会活動の中でも参照されています。 多くのアカデミックな研究は、... more